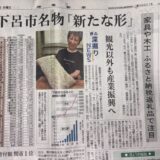減少自治体の調査から学ぶ
今回、ランキングされた高額寄付金額にどうしても目がいってしまいます。しかし、本当にまちを良くしたいと考えるならば、成功の裏にある失敗から学ぶ姿勢を大切にしたいと思います。さらに、寄付金額という「収入」だけでなく、返礼品やPRにかかる「費用」にも注目し、費用対効果が本当にあったのかを調べる必要があります。私は、そうした一次情報に触れることこそが、地域の未来を考える出発点になると感じています。
目次 非表示
1. 問題の本質に迫れる
成功事例は「一過性のヒット商品」や「キャンペーン」に左右されやすい一方、減少は「構造的な課題」が表れやすいものです。
返礼品の魅力低下、プロモーション不足、制度改正の影響など、課題の根本原因に触れることができます。
2. 改善の再現性が高い
成功要因を真似ても条件が違えば成果は出ません。しかし、減少要因を突き止め改善することは、他の自治体でも応用可能な知見になります。
(例:人気返礼品の供給不足 → どの地域でも起こり得る課題)
3. 「失敗から学ぶ」ことで持続的成長につながる
短期的な成功は派手ですが、長期的な成長を続けるには「落ち込みのパターン」と「回復策」の理解が不可欠です。
そこにこそ、持続可能性を高めるヒントが隠されています。
4. 住民理解・地域性の把握につながる
寄付金の減少は、返礼品の魅力だけでなく、
- 情報発信の弱さ
- 市場ニーズとのズレ
- 住民や事業者の巻き込み不足といった地域固有の課題を映す鏡でもあります。
地域社会の現状を知る大切な入口になるのです。
今回の「0.75倍以下」自治体
2024年度のふるさと納税で、前年度比 0.75倍以下 に落ち込んだ自治体は次の7市町です。
- 飛騨市(0.71倍)
- 養老町(0.59倍)
- 池田町(0.70倍)
- 美濃加茂市(0.55倍)
- 七宗町(0.29倍)
- 岐南町(0.22倍)
- 輪之内町(0.66倍)
これらの市町から愚直に学ぶ必要があります。
なぜ減少したのかを深掘りすることで、岐阜県全体のふるさと納税のあり方を改善し、持続可能な発展へとつなげていきたいと思います。